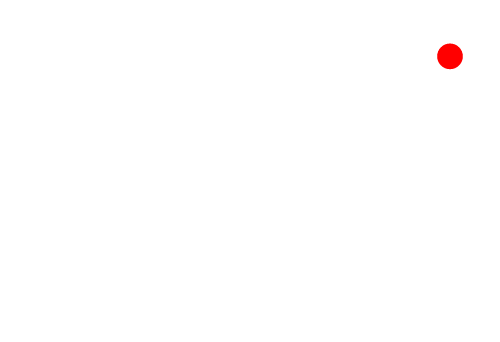映画「カメラを止めるな!」ネタバレと感想 日本人好みのインドカレーです。
ここでは映画「カメラを止めるな!」のストーリーと魅力を紹介しています。
カメラを止めるな!

これは人気出ます。
芸能人も絶賛し、小さなシアターに連日人が押し寄せるほどの人気っぷり。
その理由がわかりました。
ストーリー
※説明が難しいのでザクッといきます。
第一場面「ワンカット・オブ・ザ・デッド」
スタートして30分はぎこちないワンカットゾンビ映画です。
内容はゾンビ映画の撮影中に本物のゾンビに襲われるというもの。
撮影現場が行き詰まり、休憩をするとなんと本物のゾンビが登場。
監督はそれを「リアルだ!」と言いい、撮影する。
謎の間や、棒読みのセリフ、変なカメラワーク。
それが終わり、エンドロール。
第二場面「一ヶ月前」
監督が「ワンカットのゾンビ映画を撮影してほしい」とオファーを受ける。
それまでは再現VTRやカラオケ映像を撮っていた監督はそれを受ける。
しかし、役者はわがまま。
なかなか思うように進まない。
なんとか撮影当日を迎えるが、そこでもハプニング連発。
役者二人が事故で来れないことに。
急遽、監督自らが「監督役」になり、現場見学に来ていた監督の妻(元女優)も出演することに。
第三場面「撮影の舞台裏」
ワンカット映画の撮影スタート。
第一場面の映画「ワンカット・オブ・ザ・デッド」の裏舞台を描いています。
様々なハプニングの連発。
ワンカット撮影のため、途中で止めることはできない。
ここで「謎の間や、棒読みのセリフ、変なカメラワーク」の種明かしがあります。
紆余曲折をへて、なんとかカメラを止めることなくラストを迎えます。
エンドロール
エンドロール中に実際の撮影風景が流れます。
感想
この映画は「日本人好みのインドカレー」だと思います。
というのは「ゾンビ映画」「ワンカット映画」を元に日本人好みの演出をふんだんに盛り込んでいると感じました。
幾つかのポイントで説明します。
①適度なイライラ、適度なスッキリ。
映画には観客の感情を動かすストーリーや演出が必要です。
今作では「自己中な役者」「器の小さな監督」「無理難題を言うプロデューサー」です。
このどれもが日本で暮らす我々に当てはまります。
周りにいる自己中な人々、意見を言えない自分、無理を言う会社や社会。
それに対して、ぶっつけ本番で自分の意見をぶつける監督、我道を行く娘、役者どっぷりな妻に快感を覚えます。
観客が想像できる範囲の「イライラ」と「スッキリ」です。
海外映画のような「スターが悪を成敗」は快感ですが、リアルではない。
②「伏線の回収」が目的
約2時間という制限のある「映画」というエンターテイメントには「不必要なシーン」はありません。
特にこの映画ではそれが見事にできています。
そもそも「伏線を回収する快感」が目的なので、第一場面は「伏線用の時間」です。
ここはぐっとこらえてください。
第三幕の「回収用の時間」では快感連発で笑えてきます。
その明快さが日本人向けなのです。
「外はカリカリ、中はフワフワ」であれば全て美味しいかのように、日本人は「伏線回収好き」なのです。
③「文化祭」のような達成感
映画を観終わった時、非常に満足感を味わいました。
それが「達成感」なんだと思います。
みんなで何かを作り上げ、達成するのって楽しいですよね。
特に日本人はそれが好きだと思います。
「文化祭」や「運動会」などは記録よりも「みんなで作り上げた達成感」が重要です。
第三幕のラストでは「ハプニングを乗り越えてなんとかラストまで撮影できた達成感」でみんな笑顔です。
この感覚を僕らも知っているので、それを思い出して満足するのだと思います。
スーパーヒーローが世界を救ってヒロインとキスをしてもこの達成感は得られません。
④何層にも重なる世界
エンドロール中に本当の「撮影裏舞台」が描かれています。
それは「映画を撮影している映画の舞台裏の舞台裏」です。
ということは、世界は何層になっているのか。
層1:「ワンカット・オブ・ザ・デッド」の中で監督が撮影しようとしている世界
層2:「ワンカット・オブ・ザ・デッド」(第一場面)
層3:「ワンカット・オブ・ザ・デッド」の舞台裏(第三場面)=「カメラを止めるな!」
層4:「カメラを止めるな!」の舞台裏
なんと、第4層まであります。
それを見ている我々が第5層?
まとめ
日本人好みの演出に溢れた映画です。
なので誰が見ても満足出来ると思います。
しかも題材が「ゾンビ」であれば「どんな映画だろう」と考えてしまい、良いスパイスになります。
「撮影の舞台裏のハプニング」を描いているので芸能界からの評判が良いのも頷けます。
おすすめ映画
ワンカットなホラー映画。
「サイレント・ハウス」

カメラを止めちゃダメだ!
「REC」

舞台裏をネタばらしする映画
「キャビン」

この記事を書いた人
tetsugakuman
基本的にはダークな映画を好む。
スリラーバイオレンスホラーミステリーサバイバルSFアクションなど。